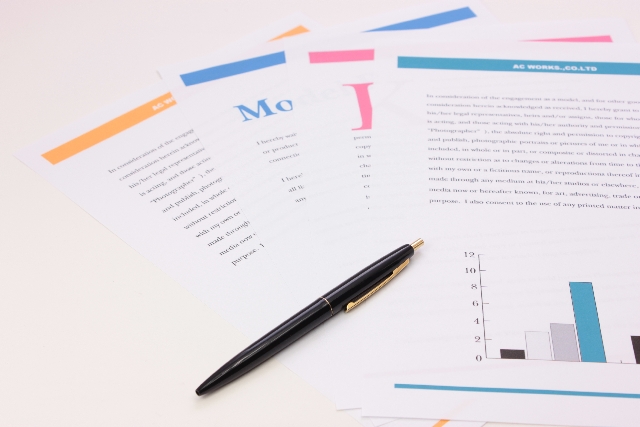


先月、4年勤務の会社を退職し、留学を考えています。出発までの失業保険の受け取りについて考えております
先月12月に4年間勤務した会社を退職いたしました。
今年の4,5月辺りから海外に語学留学で行くので、自己都合という形で、退職いたしました。
出発は、4,5月以降にずれ込むかも知れないのですが、正直もらえるなら、失業保険の給付をもらいたいです。
出発が4,5月だとすると、給付手続きをして、給付を受け取れる月は1,2か月分だと思うのですが、
再就職手当のように、減額でもいいので、一括でもらえるとか、もらえそうな方法はないでしょうか?
以前、ハローワークに同様の質問をしたところ、
失業手当は、再就職する方の為の制度であり、あなたのような方には案内も質問の回答も差し上げられません。と対応されてしまいました。
僕の理由は、不純だと思いますが、1年間の給付資格があるのなら、活用したいです。
やはり出発まで、地道に1か月ずつ、手当をもらうしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。
先月12月に4年間勤務した会社を退職いたしました。
今年の4,5月辺りから海外に語学留学で行くので、自己都合という形で、退職いたしました。
出発は、4,5月以降にずれ込むかも知れないのですが、正直もらえるなら、失業保険の給付をもらいたいです。
出発が4,5月だとすると、給付手続きをして、給付を受け取れる月は1,2か月分だと思うのですが、
再就職手当のように、減額でもいいので、一括でもらえるとか、もらえそうな方法はないでしょうか?
以前、ハローワークに同様の質問をしたところ、
失業手当は、再就職する方の為の制度であり、あなたのような方には案内も質問の回答も差し上げられません。と対応されてしまいました。
僕の理由は、不純だと思いますが、1年間の給付資格があるのなら、活用したいです。
やはり出発まで、地道に1か月ずつ、手当をもらうしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。
ハローワークの
>失業手当は、再就職する方の為の制度であり、あなたのような方には案内も質問の回答も差し上げられません。
との対応は、海外に語学留学することが決まっているのに、失業給付を受け取る資格はありません、という主旨での回答であり、まとめてもらうとか、地道に1回ずつもらうとかの問題ではありません。
そもそも、受給資格がないというだけのことです。活用のしようがありません。
受給期間延長の理由に海外留学は相当しません。青年海外協力隊(でしたっけ?)のボランティアに参加するのは大丈夫ですが。まあ、個人的にはそれもなんとなくおかしいような気がしますが。なんで、青年海外協力隊だけなのか?他のボランティアではいけないのか?
また、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再度、被保険者になった日の間が1年を超えると、それまでの被保険者期間は無効になります。1年留学するのであれば、確実に無効になりますから、念のため。
>失業手当は、再就職する方の為の制度であり、あなたのような方には案内も質問の回答も差し上げられません。
との対応は、海外に語学留学することが決まっているのに、失業給付を受け取る資格はありません、という主旨での回答であり、まとめてもらうとか、地道に1回ずつもらうとかの問題ではありません。
そもそも、受給資格がないというだけのことです。活用のしようがありません。
受給期間延長の理由に海外留学は相当しません。青年海外協力隊(でしたっけ?)のボランティアに参加するのは大丈夫ですが。まあ、個人的にはそれもなんとなくおかしいような気がしますが。なんで、青年海外協力隊だけなのか?他のボランティアではいけないのか?
また、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再度、被保険者になった日の間が1年を超えると、それまでの被保険者期間は無効になります。1年留学するのであれば、確実に無効になりますから、念のため。
会社都合で辞めて、失業保険を今は、もらっていて、残り5ヶ月くらいはもらえるんですけれど、新しく会社に決まりそうで、
今もらっている失業保険のお金より少ない給料なので、就職してから、半年くらいで辞めてしまった場合は、今度もらう失業保険の金額は、新しく入社した少ない給料の金額で計算されてしまうのでしょうか。
前の失業保険の金額は、関係なくなってしまうのでしょうか。雇用保険は、強制的に加入しなければならないのでしょうか。
今もらっている失業保険のお金より少ない給料なので、就職してから、半年くらいで辞めてしまった場合は、今度もらう失業保険の金額は、新しく入社した少ない給料の金額で計算されてしまうのでしょうか。
前の失業保険の金額は、関係なくなってしまうのでしょうか。雇用保険は、強制的に加入しなければならないのでしょうか。
雇用保険の支給金額は失業前6ヶ月間のお給料によって決まりますので、半年働いたら当然新しい会社のお給料により換算されます。
前の失業保険の金額は関係なくなります。
そして、短時間のパートやアルバイトならば雇用保険には入りませんが、正社員なのだとしたら当然雇用保険には入らなければなりません。
個人的意見ですが、入社前から「半年で辞めそう」などと思っている会社には入らない方がいいと思いますよ。
前の失業保険の金額は関係なくなります。
そして、短時間のパートやアルバイトならば雇用保険には入りませんが、正社員なのだとしたら当然雇用保険には入らなければなりません。
個人的意見ですが、入社前から「半年で辞めそう」などと思っている会社には入らない方がいいと思いますよ。
再就職祝い金を貰える条件を教えて下さい。
現在、在職中で今月末で退職します。会社都合の退職です。
ですが、面接を受け採用され11月1日からアルバイトとしてですが仕事が決まりました。
この場合は正社員としてでの就職ではないので祝い金は貰えないのでしょうか?
失業保険も貰わずアルバイトが決まった場合は支払っていた雇用保険はゼロになるのでしょうか?
無知でわからなく質問しました。
詳しくわかる方、すいませんが教えて下さい。
現在、在職中で今月末で退職します。会社都合の退職です。
ですが、面接を受け採用され11月1日からアルバイトとしてですが仕事が決まりました。
この場合は正社員としてでの就職ではないので祝い金は貰えないのでしょうか?
失業保険も貰わずアルバイトが決まった場合は支払っていた雇用保険はゼロになるのでしょうか?
無知でわからなく質問しました。
詳しくわかる方、すいませんが教えて下さい。
再就職手当を受給するためにはハローワークに求職の申請をして、受給資格者にならなければいけません。
それで、11月1日から職が決まっているのなら失業状態ではないと判断されて受給資格者にはなれません。
アルバイト、正社員は関係ありません。
支払っていた雇用保険がゼロになるという疑問ですが、その仕事が雇用保険に加入しているかどうかです。
離職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できますのでそれから言えばゼロにはなりません。
加入していなくて1年を経過すればそれまで加入していた期間はゼロになってしまいます。
それで、11月1日から職が決まっているのなら失業状態ではないと判断されて受給資格者にはなれません。
アルバイト、正社員は関係ありません。
支払っていた雇用保険がゼロになるという疑問ですが、その仕事が雇用保険に加入しているかどうかです。
離職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できますのでそれから言えばゼロにはなりません。
加入していなくて1年を経過すればそれまで加入していた期間はゼロになってしまいます。
一般的なキリスト教会での十一献金(収入の1/10を教会に納める事)についての質問です
(1)十一献金は義務、任意のどちらですか?義務だった場合十一献金を拒めば教会からどの様な制裁がありますか?
また恐喝にあたる恐れはないですか?
(2)収入の1/10の収入とは、基本給、手取り、食費など生活に必要な費用を除いた残り、こずかいのどれですか?
(3)お年玉や宝くじ、商品券、失業保険も十一献金の対象になりますか?
(4)お金以外のものを譲り受けた場合はどうなりますか?
(5)十一献金の用途の明細は、信者に公表されますか?(教会の経費にいくら使ったか、牧師の懐にいくら入ったか等)
(1)十一献金は義務、任意のどちらですか?義務だった場合十一献金を拒めば教会からどの様な制裁がありますか?
また恐喝にあたる恐れはないですか?
(2)収入の1/10の収入とは、基本給、手取り、食費など生活に必要な費用を除いた残り、こずかいのどれですか?
(3)お年玉や宝くじ、商品券、失業保険も十一献金の対象になりますか?
(4)お金以外のものを譲り受けた場合はどうなりますか?
(5)十一献金の用途の明細は、信者に公表されますか?(教会の経費にいくら使ったか、牧師の懐にいくら入ったか等)
献金に限らず、すべての捧げもの(祈り・賛美・奉仕・・・)は、私たちの「神への感謝」の現われです。多く感謝している人は多く捧げるし、あまり感謝していない人はあまり捧げません。基本的に、人から強制されるもの(義務)ではなく、自主的なもの(任意)です。
什一献金は、旧約の時代には義務でした(他にも捧げ物に関しての規定はたくさんありました)が、新約の時代にそれが適用されるかは、解釈が別れます。イエス様ご自身は、10分の1を捧げるように言っていますが、十字架にかかる(あがないが完成する)前の“旧約聖書にのっとった”発言であり、十字架後はイエス様も弟子たちも「10分の1」には触れていません(肯定も否定もしていません)。Ⅱコリント9:7は「ひとりひとり、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めたとおりにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。」と書かれています。
注意しないといけないのは、“羊のなりをした”貪欲な狼牧師です。具体的には↓
給料明細を信徒に持って来させ、具体額を支持する
多額の献金をした人を皆の前で褒め、少額の人に罪責感を与える
何かにつけて献金を要求する(イースター、クリスマス、夏季冬季ボーナス、誕生日、会堂献金、その他特別献金など)
まるで献金をギャンブルの掛金のように「捧げた分だけ祝福されるから」と言って多く捧げさせる
手持ち金が少ないと、「約束献金(あとで払う献金)」と言って用紙に金額を記入させ、持っていないものまで取り立てようとする
うまいことを言って、信徒の財産(土地などの不動産)を奪い取る
会計報告をしないで、牧師の独断で献金を自由に使う・・・・など。
什一献金は、旧約の時代には義務でした(他にも捧げ物に関しての規定はたくさんありました)が、新約の時代にそれが適用されるかは、解釈が別れます。イエス様ご自身は、10分の1を捧げるように言っていますが、十字架にかかる(あがないが完成する)前の“旧約聖書にのっとった”発言であり、十字架後はイエス様も弟子たちも「10分の1」には触れていません(肯定も否定もしていません)。Ⅱコリント9:7は「ひとりひとり、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めたとおりにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。」と書かれています。
注意しないといけないのは、“羊のなりをした”貪欲な狼牧師です。具体的には↓
給料明細を信徒に持って来させ、具体額を支持する
多額の献金をした人を皆の前で褒め、少額の人に罪責感を与える
何かにつけて献金を要求する(イースター、クリスマス、夏季冬季ボーナス、誕生日、会堂献金、その他特別献金など)
まるで献金をギャンブルの掛金のように「捧げた分だけ祝福されるから」と言って多く捧げさせる
手持ち金が少ないと、「約束献金(あとで払う献金)」と言って用紙に金額を記入させ、持っていないものまで取り立てようとする
うまいことを言って、信徒の財産(土地などの不動産)を奪い取る
会計報告をしないで、牧師の独断で献金を自由に使う・・・・など。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
関連する情報